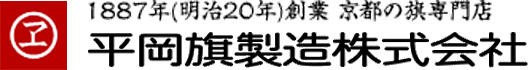【2025年新入社員奮闘記2】「色」っておもしろい!旗の仕事で知った日本の色の魅力
皆さんお久しぶりです、新入社員のキタクボです!
私も入社から半年になります。
様々な経験を経て、自身の成長を感じると同時に、まだまだ知らないことが多いことを実感している今日この頃です。
今回は『色』についてのお話をさせていただこうと思います!
色と言われて皆さんが思いつくことはどんなことがありますか?
私は色の呼び名を思い浮かべます。
その理由は、純粋に素敵な呼び方がされている色がたくさんあるからです。
銀朱(ぎんしゅ)、常磐(ときわ)、薄紅梅(うすこうばい)、浅縹(あさはなだ)、など、日本の伝統色の名前は美しいなと常々思います。
薄紅梅など名前からどんな色合いかイメージがしやすいものもあれば、常磐や浅縹のようにすぐにピンとこないような名前の色もあり、どんな色なのか、なぜその名前が付けられたのかなどを調べるのもとても面白いです。
学校や会社の旗なども、えんじ色や紺色、紫色など鮮やかで明るい色から落ち着いた色まで様々なものがあります。
学校や企業などは「自分たちの色(チームカラー)」をお持ちのところもあります。
そのカラーも『○○グリーン』のように学校名や会社名を冠する名前を使っていて、皆さんに愛されてるものが多いです。
この仕事をするようになってから、普段目にする広告や旗の色ひとつにも、代々引き継いできたこだわりの色が使われているのをひしひしと感じます。
色の意味といえば、例えばお寺の仏旗のカラフルな色合いにも様々な意味があります。
- 青は仏さまの髪の毛の色。
- 黄は燦然と輝く仏さまの身体の色。
- 赤は仏さまの情熱ほとばしる血液の色。
- 白は仏さまの説法される歯の色。
- 樺は仏さまの聖なる身体を包む袈裟の色。
このように、色一つであってもそこには様々な歴史や思いが込められています。
私たちも旗のご注文をいただくときには、「この色で」とご指示いただくことがあります。
そういうときには、色見本帳というものを使って、どの色が近いか確認をして進めていきます。


染めで特定の色を表現するのは、すごく難しいことを私も染め体験や仕事を通じて学びました。
色の濃さひとつを取っても、淡い色は塗りムラが出やすいので均一に染めるのが難しく、また色味のなかでも水色などは、色を再現するのが難しいそうです。
染めるためには洗ったり熱を加えたり様々な行程を経ていますので、染料そのままの色とはいかないのが大変です。
様々な色を表現するため、職人が知識と経験をもって、糊と染料を混ぜたときの反応や蒸し水洗後の色を予測しながら調合しています。
こちらは染体験の時、実際に染めたものです。

塗っているときは柿のような鮮やかな鮮やかなオレンジ色だった染料が、蒸し水洗を経て少し落ち着いた黄色味のある色になりました。

出来上がったときにも、あのオレンジがこんな色になるんだととても驚きました。
新しい染めの技法ができると同様に、染料の成分や後継者問題などで再現ができなくなってしまうものもあります。
旗が古くなってきたので新調をという依頼はよくありますが、技術的にできなくなってしまっていたら悔しいものですね。
ただ、私たちも代替案がきちんとご提案できるように日々精進しております!
私も知識はまだまだ足りないところもありますが、一人前になれるよう学び続けたいと思います!
=============================
お問い合わせはコチラ↓
または075-221-1500までお電話ください。
============================
今回のブログはキタクボが担当いたしました。